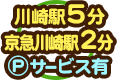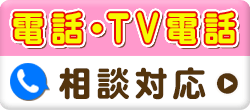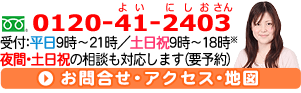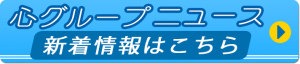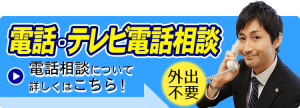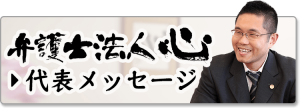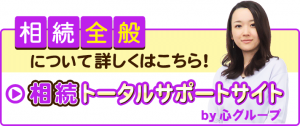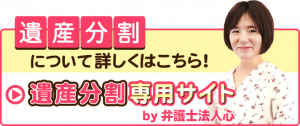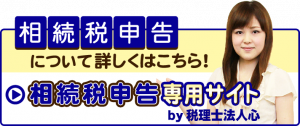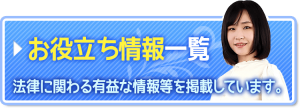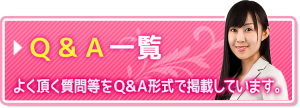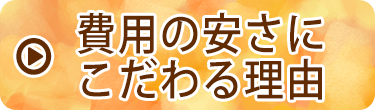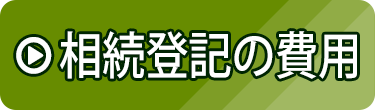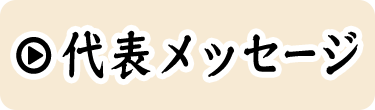遺産分割がまとまらない場合、相続登記はどうすればよいか
1 遺産分割がまとまらない場合の相続登記への対応方法
結論から申し上げますと、遺産分割がまとまらず、期限までに相続登記ができない場合には、一旦法定相続分での登記をするか、または相続人である旨の申出を行います。
これにより、一旦罰が科されることを免れることができます。
その後、遺産分割が完了したら、その日から3年以内に相続登記をすることで義務を果たしたことになります。
遺産分割がまとまらないことが想定される場合には、一旦法定相続分での相続登記をするか、相続人である旨の申出をしておくと安全です。
以下、相続登記の期限と、相続登記を期限内に行わなかった場合の扱いについて詳しく説明します。
2 相続登記の期限
⑴ 法定相続分で相続登記をする場合
不動産登記法第76条の2第1項によれば、原則として「相続により所有権を取得した者は」「当該自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」とされています。
そして、この相続登記が法定相続分に応じてされたものである場合、その「後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」と不動産登記法第76条の2第2項に定められています。
参考リンク:e-Gov法令検索(不動産登記法第76条の2)
つまり、まず相続の開始によって当然に法定相続分を取得した段階で、相続開始から3年以内に一旦相続登記を行っておけば、もし遺産分割が長引いても相続登記の義務との関係においては問題がないといえます。
なお、相続開始の日から3年以内に遺産分割がまとまる場合には、遺産分割後に1回相続登記をすれば問題ありません。
⑵ 相続人である旨の申出をする場合
不動産登記法第76条の3第1項によれば、「前条第一項の規定(筆者注:相続登記の義務を定めた規定)により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる」とされています。
そして、不動産登記法第76条の3第2項により、「前条第一項に規定する期間内(筆者注:相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内)に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみな」されます。
参考リンク:e-Gov法令検索(不動産登記法第76条の3)
この届出をした場合も、遺産分割が完了したら、その日から3年以内に相続登記を行えば問題はありません。
3 相続登記を期限内に行わなかった場合の扱い
「正当な理由がないのに」相続登記の「申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と定められています(不動産登記法第164条)。
「正当な理由」にあたる事情としては、相続人がとても多く調査や確定に長時間を要する場合や、重い病気にかかってしまい登記の申請や申出ができない場合、経済的に困窮していて登記や申出ができない場合というものがあると解釈されています。
注意しなければならないのは、遺産分割がまとまらずに長引いているという事情は、不動産登記法第164条の「正当な理由」にはならないという点です。
相続人間で遺産分割について揉めてしまうと、場合によっては遺産分割がまとまるまで数年程度を要するということがあります。
この間に相続登記の期限が経過してしまうと罰が科されてしまう可能性があるため、少しでも遺産分割で争うことになりそうであれば、すぐに法定相続分での相続登記をするか、相続人である旨の申出をするべきであるといえます。